番外/映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉 [草創期の映画]
今でもご訪問くださる映画好きのみなさまに感謝申し上げます。
左袖の「マイカテゴリー」は「章」になっております。
番外/映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉

過日、東京・府中市の多摩交流センターで、全国生涯学習ネットワーク他主催による「第181回、多摩発・遠隔生涯学習講座」において表記のテーマでお話させていただいた映画技術史を要約しました。
038 「映画」の未来は見えたか? [草創期の映画]
038 「映画」の未来は見えたか?
ノンフィクションとフィクション-1
●19世紀末パリ、モンマルトル ムーラン・ルージュ〈写真右〉
1895(M28)年12月28日、リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」初公開によって「映画」は誕生したとされているのですが、実は<動く写真>の研究者や発明した本人たちも、「映画」が進む方向性をはっきりと認識していた訳ではなかったらしいのです。それほど「映画」というメディアは画期的な発明だったのです。(インターネットもある意味ではそんな感じでしたね)
とはいえ「映画」は動き出しました。機械の発明レースが終わって、さあ、今度はそれをどう使うか。フランスではリュミエール兄弟が、ジョルジュ・メリエスが。アメリカではトーマス・エディスンが、それぞれの思惑で行動を起こしました。
●ノンフィクションに向かったリュミエール兄弟。
リュミエール兄弟が「シネマトグラフ」で目指したものは、<生命を記録し、自然をありのままに捉えること>でした。シネマという言葉もラテン語の<動き>からとったものでした。リュミエール兄弟は、現在自分たちが存在している時代というものに目を向けました。時あたかも19世紀のどんづまり。あと5年で新世紀です。
それまでの歴史は紙に書かれたものでした。
<自分たちの「シネマトグラフ」は、その世紀の変わり目を写し止めることが出来るのではないか>。
「シネマトグラフ」なら、その当時の「現代」の様子を動く写真で記録できます。その動く写真は時間とともに過去の歴史になります。リュミエール兄弟の照準は、"19世紀末の動く世界史"をまとめ上げることに向けられました。
これは、現在の姿をとどめておいて、あとで時間を遡ってそれを見る、という目的が明確です。「シネマトグラフ」が初公開された1895年は、イギリスの小説家、H・G・ウェルズのSF小説「タイムマシン」が発表された年でもあります。
リュミエール兄弟がそれを意識していたかどうかに関係なく、「映画」はこのあと表現技法が次々と開発されていくに従って、時空間を自在に飛翔するメディアに育っていきます。このSF小説と映画という新技術が同時期に生まれたという符合は偶然とは思えず、映画の未来を予見するもののように感じるのです。

●リュミエール兄弟と「シネマトグラフ」
リュミエール兄弟は「シネマトグラフ」初公開が一段落すると、その年の内に20人の技師を募集。1896(M29)年の年明け早々から、早速養成を始めました。「シネマトグラフ」は撮影機と映写機の兼用ですから単なるカメラマンの養成ではありません。撮影の操作とフィルム現像のやり方を習熟してもらわなければなりません。また記録性重視ですから、あくまでも一定スピードで自然の状態をそのまま撮る、映す。これが原則です。そのための訓練も行われました。
また、世界の主要都市に配置するために200台もの「シネマトグラフ」の製造を開始しました。これは20人の技師に携行させるほか、世界各国の興行会社に配置するためでした。リュミエール兄弟のやり方はエディスンのように機械そのものを売るのではなく、興行代理人を立て、各国の興行を代行させて利益を配分するやり方でした。
●わずか1年で世界を制覇した「シネマトグラフ」。
こうして春から「シネマトグラフ世界紀行」取材班の活動が始まりました。まずイギリスを皮切りにイタリア、ドイツ、スイス、アメリカと進められ、初夏までには日本、オーストラリア、メキシコ、インドにまで達しました。また興行も、エジプト、トルコ、ポルトガル、デンマーク、ノルウェーにまで及びました。

●リュミエール社のカメラマン ●コンスタン・ジレルが撮影した稲畑家団らんの様子
「シネマトグラフ」の技師たちは、訪問先の国々でその地方独特の風景や風習を写しとめました。そして撮影したフィルムはすぐに現像して、現地の人たちに上映して見せました。人々は住んでいる自分たちの村の様子や写された〈分身〉がスクリーン上で動くのを見てビックリ。話題はどんどん広がり、リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」は爆発的な勢いで、わずか1年くらいの間に一挙に世界中に波及することになったのでした。結果的に国際的PR活動の効果をもたらしたわけです。
この世界行脚による撮影記録は、50フィート(約17メートル)のフィルム358本に及ぶ成果を挙げました。これらの動く写真記録は、今日、言葉通りのタイムカプセルとして、当時をしのぶ貴重な文化遺産となっています。
記録されたフィルムの中には、ヴェルサイユ行きの汽車の窓から撮影した風景。走る列車の昇降口から見るナイル川。昇降するエッフェル塔のエレベーター。トンネルに入っていく機関車の様子、などがあります。カメラ自体はあくまでも固定でありながら、早くもパノラマ撮影(パノラミング)、移動撮影(トラベリング)が試みられていたのです。
リュミエール兄弟の目指した記録としての映画の利用法は、今日、「記録映画」と呼ぶ映像の基本ジャンルとして確立しています。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
●トリック撮影の芽生えも早かった。
〈動く写真〉に消極的だったエディスンが、周りに遅れをとったと悟ってからの行動は素早く、直ちに「ヴァイタスコープ」を開発して初公開に臨んだ(前回の記事参照)のですが、上映するフィルムはとりあえず「キネトスコープ」用に作られた1分足らずのフィルムを10数本上映して見せたにすぎませんでした。
「ブラックマリア」と称される撮影スタジオまで持ちながら、その後もしばらくの間エディスンは「ヴァイタスコープ」用の長尺映画の製作には手を付けませんでした。エディスンは「映画」というニューメディアの商業的価値を読み切れず、映画は単なる見世物と考えていたようです。

●トーマス・エジソンの「ヴァイタスコープ」1896
事実、エディスンの映画は、1分足らずのフィルムを数本続けて、ボードヴィルの幕間や終わりに上映されていました。そこでは舞台下のオーケストラボックスにピアノを設置して、即興の音楽が付けられていました。映し出されるものは相変わらずで、自然の風景、ダンス、アクロバットなど。
エディスンは、これでは「キネトスコープ」の二の舞になっていつか飽きられてしまう、という懸念は持っていましたが、それ程危機を感じていたわけではないようです。彼が困ると、いつも周りの誰かがうまく取り計らってくれたからでしょう。
そうした中で評判を呼んだフィルムがありました。「スコットランド女王メアリの処刑(1895)」。これは妹のエリザベス1世から死の宣告を受けたBloody Maryの処刑という歴史上の情景を再現したものです。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
ご覧になってお分かりの通り、ここでは止め写しという手法が使われています。つまり、役人が斧を振り上げたところでカメラを止め、役者はそのままのポーズでいる間に女性を人形にすげ替えて撮影を続行するというものです。これはフィルムを切ってつないだ訳ではないので編集ではありません。編集の概念はもっと後の話になります。これはもっとも単純なトリックですが、この頃すでにこうしたトリックが発見されていたということは注目に値します。現在それを分かっている私たちが見ても、実に巧妙に撮影されていると思います。
こうした歴史上の事件の再現フィルムは、エディスン社に限らず、リュミエール兄弟もパテ社もゴーモン社も例外なく作品ジャンルの1群に加えていきます。まだ、監督もスターも生まれていない時代。歴史への興味が人気を呼んだからですが、その魅力は、映画と言うメディアが、イミテーションでありながら過去の時間と空間を自在に現在に甦らせてくれるからに他なりません。
エディスン社の「ヴァイタスコープ」も、「シネマトグラフ」のすぐ後を追って世界に広まっていきました。
●50フィート、上映時間1分の映画からの脱却。
さて、フィルムが50フィートで1分程度のものしか作れないということに疑問を感じる段階が、リュミエールの側にもエディスンの側にも間もなくやってきます。双方ともネタが尽きてくると、必然的にストーリーのあるものを作りたいと考えるようになりました。ここで初めて50フィートの2倍、3倍・・・という長尺物に考えが及び始めました。
映画フィルムの大手メーカーに成長したイーストマン・コダック社は1889年にすでに200フィートのフィルムを開発していましたし、もともと写真業であるリュミエール社も自社で長尺フィルムを作れる環境を擁していました。
当時、映画はまだ撮影技師がカメラを回せば作れるレベルでしたが、長尺物ではそうは行きません。そこで対象となったのは舞台でした。舞台の出し物をステージの前にカメラを固定してそのまま撮影するのです。最初の頃の長編映画はそんなところから始まりました。撮影の現場では撮影技師(カメラマン)が必要な指示を出していました。監督と言う職業はまだ生まれていません。
●リュミエール社のキリスト受難劇 1897
長尺フィルム自給の環境が整うと、ノンフィクションを主力にしていたリュミエール社も、「イエス・キリストの生涯と受難」(1897)に代表されるフィクション映画にも着手します。これは当時舞台で演じられていたパントマイムによる「活人画」の趣向を野外劇に仕立てて、それをそのまま撮り続けたものですが、これは13の場面で800フィート(約250m)にもおよぶ大作でした。パントマイムには音楽が付いていましたから、この映画も音楽の演奏付きで上映されたと思われます。
また、当時のニュースや有名になった事件、あるいは歴史など、物見高い人々が実際に見てみたいという願望を満たす再現フィルムも多数作られました。再現フィルムは役者が演じたので、極めて演劇的でした。つまりノンフィクションに似せたフィクションです。
映画はこのように、まずは演劇を真似て物語を語ることに利用され始めたのでした。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
●フィクションに向かったエディスン社。
「発明」という技術開発を終え、今や「創造」という表現の段階に入った映画。その中でエディスンの立場は、映画を事業として成功させるというプロデューサー的役回りに変わりました。彼はそれまでに力を入れて来た鉄鉱石選別の機械化事業が思うような利益を上げていないこともあり、「キネトスコープ」以来新しく手掛けた〈動く写真〉、つまり「映画」をエディスン社の事業のメインに置く必要を感じ始めていました。
エディスンの考える映画事業の第一歩は、それまでに進めて来た映画用カメラと映写機に関する特許商法と、「キネトスコープ」のために作ったフィルムの権利を確立することでした。そのために、法律関係を任せてあるリチャード・ダイヤーとフランク・ダイヤー兄弟の「ダイヤー&ダイヤー社」弁護士軍団にはこれまで以上に張り切ってもらわなければなりません。そして大事なことは、大衆層からセレブリティまで、人々が喜ぶ面白い映画を作ることでした。
エディスンは元来通信技師から身を起こした人ですから、どちらかといえば工学系。その彼にとって非常に幸運だったことは、20世紀を迎えた直後から、フィルムメーキングに特別な才能をもつクリエーターたちと出会うことができたことでした。
彼らは生まれて間もない映画を、それまでになかった新しい表現媒体として捉え、活用しようと考えます。撮影機を窮屈なスタジオから野外に持ち出し、緊迫感あふれる物語をつむぎ始めます。それは記録ではなくアクションだったいうところが、いかにもアメリカらしいと思うのです。
つづく
★次回はフィクションの極み、トリックの天才ジョルジュ・メリエスです。
039 映画は本来、トリッキー [草創期の映画]
039 映画は本来、トリッキー
ノンフィクションとフィクション-2
●ボワ大通りにおけるパリ・グランプリの様子 リュミエール撮影 1899(M32)
前回からの続きです。
映画創生期における最初の牽引者と目されるのは、技術的にはそれを発明したフランスのリュミエール兄弟。作品づくりではジョルジュ・メリエス。そして事業として発展させたのはアメリカのトーマス・エディスンといえると思いますが、リュミエール兄弟とエディスンの二人についてのあらましは前回お話しましたので、今回はジョルジュ・メリエスです。●ジョルジュ・メリエス
●自分には自分に似合う撮影機を。
ジョルジュ・メリエスはリュミエール兄弟の「シネマトグラフ」初公開に招待されて、初めて目にする「動く写真」に感動し、これこそ自分の所有するロベール・ウーダン劇場のステージをはるかに魅力的なものにする仕掛けだと考えました。そこで、1895(M28)年12月28日のあの晩、上映が終わるとすぐに兄のアントワーヌ・リュミエールに「この機械をぜひ1万フランで譲ってほしい」と頼みました。
ところがアントワーヌは「これで私は興行を続けたいと思いますし、中身は秘密ですから売れないのですよ」とやんわり。「古い付き合いじゃないですか」と食い下がっても、「売ってもらえなかったことを感謝すべきかもしれませんよ。しばらくは珍しがられるかも知れませんが、すぐ飽きられてしまうでしょうからね」と断られてしまったのでした。●リュミエール兄弟
●サン・マルタン大通りのリュミエール映画館 1896年頃
実際、他では2万、5万という声もかかったのに、リュミエール兄弟は「シネマトグラフ」を売ることはありませんでした。間もなくメリエスのライバルになるシャルル・パテもレオン・ゴーモンも断られた一人でした。
リュミエール兄弟にしてみれば、一人にだけ売ってあげたとしてもいずれはみんなに分かることだから、これは売らないことが公平、と考えたのでしょう。
それなら仕方がない。駄目なら自分で用意するまでさ。メリエスはイギリスで〈動く写真〉を作り始めた、光学機械の研究家ロバート・ポールに頼むことにしました。もちろんロンドンへは看板女優で彼の愛人でもあるジュアンヌ・ダルシー嬢がいっしょです。●ロンドンの光学機器商・映画製作者 ロバート・ポール
ロバート・ポールはすでに述べたように、1894(M27)年末からロンドンで、エジソン系列の「キネトスコープパーラー」を開いていたのですが、覗き見式「キネトスコープ」のフィルムを上映するために、自分で「バイオスコープ(キネトスコープ・ポール)」と名づけた映写機を開発したことでエディスン側からフィルムの供給を止められていました。
ポールはへこたれずに、かえって自分でフィルムを制作することを考え、その結果、ドキュメンタリー映画の先駆となるのですが、彼は「バイオスコープ」を改良した新式の「アニマトグラフ」をわずか1,000フランでメリエスに譲ってくれた上、エディスン社のフィルムと自分が作ったフィルムも分けてくれました。
それらの機材とフィルムは、早速ロベール・ウーダン劇場のステージを飾りました。1896(M29)年4月6日。この日はジョルジュ・メリエスにとって、まさに至福の日となりました。
メリエスも自分で映画を撮るつもりでしたから、技術者を雇うとその映写機の機構を生かして撮影機を作り上げてしまいます。メリエスが使い勝手のいいように作り上げられたこのカメラは「キネトグラフ・メリエス」と名づけられました。これでメリエスにも、思うままに映画を作り、それをステージで活用する手段が整った訳です。
●何ごとも、はじめは模倣から
この年、メリエスは早速仲間や友だちを集めて1本のフィルムを撮影しました。それはテーブルを囲んでのトランプ遊びの情景でした。そうです。リュミエール兄弟のフィルムにありましたね、「エカルテ遊び(かるた遊び)」。メリエスは全くの真似ではまずいと考え、ビールではなくワインに変えましたが、状況は全く同じ。この他、庭師の水撒きやホームに到着する列車も撮影しました。みんなリュミエール兄弟が撮ったものです。まあ、はじめは小手調べといったところでしょう。
さて、小手調べのネタが尽きるとメリエスは、カメラマンと35キロの「キネトグラフ」を携えて勇躍パリの街に繰り出しました。オペラ座広場、フランス座広場、イタリアン大通り、ブーローニュの森、コンコルド広場、サン・ラザール駅、バスチーユ広場など、毎日のようにパリの名所が次から次へと撮影されていきました。
7月恒例の別荘での休日もほとんど撮影に費やされました。周辺の海岸や埠頭で、船の航行や荷降ろしなどの情景が撮影され、ル・アーブルではリュミエールのフィルムにもあるようなゴンドラのへさきからの移動撮影も試みられました。●フォード1号車に乗るヘンリー・フォード 1896
また「自動車の出発」というフィルムでは、登場したばかりのガソリン自動車が撮影されました。それまで自転車と馬車と電車だけだった街頭風景に、初めて自動車が登場したのです。メリエスのこのフィルムが、映画に自動車が登場した最初のフィルムかもしれません。その自動車のスタイルも、上の写真のようなものでした。これらの映画はロベール・ウーダン劇場の出し物の幕間に上映され、好評を博しました。
(ちなみにT型フォードは1908年登場ですから、一般に古いサイレント映画でおなじみの屋根つきの自動車が写っていれば、それは1908年以降に撮影されたものと言うことができます)。
●ジョルジュ・メリエス所有のロベール・ウーダン劇場とポスター
●トリックに向かったジョルジュ・メリエス
先人の模倣からはじめ、身の周りを撮りまくったメリエスは、そこでようやく本当にやりたかったことに着手しました。マジシャンでロベール・ウーダン劇場の支配人兼演出家兼美術監督兼主演俳優でもあるメリエスにとっての映画が本当に目指すところは、実写ではなく「芸術」でした。
その中にはリュミエール兄弟やエディスンもやっていた、演劇形式による事件の再現フィルムもありました。けれどもメリエスのねらいはなんと言ってもファンタジーの世界を芸術的に創り上げることでした。彼はフィクションの中でももっとも先鋭的なトリックの分野を目指したのです。
彼の頭の中では、いろいろな構想が渦巻いていました。アイディアはすごくても、ステージでは技術的に困難で見送ってきたイリュージョンが山ほどありました。映画という光学的な新しい表現媒体を手にした今、それを実現できるかも知れないのです。
こうなるとフィルムはいくらあっても足りません。幸い撮影用のフィルムは、ロンドンのロバート・ポールがニューヨークのイーストマン・コダック社から箱ごと購入したものをそっくり回してくれました。こうして1896年の末、メリエスの最初のトリック映画が生まれました。
●初歩的なトリックは3つの国で、偶然の一致
「ロベール・ウーダン劇場における婦人の雲隠れ」と呼ばれるその映画は、ある有名な魔術師の出し物をそのまま頂いて映画にしたものでした。照明というものが無い時代ですから、モントルイユにあるメリエスの家の庭に室内のセットを…と言っても書割ですが・・・を組んで、室内の情景が例によって1シーン1カットで撮影されました。魔術師役はいつもの通りメリエス自身。婦人役はジュアンヌ嬢です。
●ロベール・ウーダン劇場の看板女優 ジュアンヌ・ダルシー
●メリエスの最初のトリック映画「ロベール・ウーダン劇場における夫人の雲隠れ」1896
背景には布に書いた居間の絵を広げ、花柄ドレスのジュアンヌ嬢が椅子に掛けています。魔術師登場。何やら怪しげな呪文を唱えて手にした布を彼女に掛け、さっと取り払うと、彼女の姿は跡形もありません。そこでもう一度布を掛けて振り払うと、何と、彼女の姿はおぞましい骸骨に変わっているではありませんか。更にもう一度呪文を唱えて布を振り払うと、どうでしょう。そこには何事も無かったかのように艶然とほほ笑んでいるジュアンヌ嬢の姿が……というトリックです。
これは前回、エディスン社で作られた「スコットランド女王メアリの処刑」(前回の動画参照)と同じ止め写しと置き換えの手法です。アメリカではこの技術の発見の経緯は分かりませんが、メリエスはこのトリックの発見について次のように語っています。
「オペラ通りを撮影していたらフィルムが引っかかり、直すのに1分ほどかかりました。その後そのまま撮影を続けたのですが、現像してみたら、バスチーユ行きのバスがカラスに、歩いている男が女に変わっていたんです」
カメラは三脚に据えたまま。カメラ操作を止めている間に、情景が変わってしまった訳ですね。
面白いことに日本の映画監督マキノ雅弘氏の回顧録「映画渡世・天の巻」にも同じようなエピソードが載っています。お父さんのマキノ省三氏が忍術映画を考えたきっかけです。
「フィルムチェンジをしている隙に、役者が一人小用のためにその場を離れたのを知らなかった。フィルムチェンジが終わって撮り続けたものを後でつないで見たら、役者が一人消えていた。そこから人物がパッと消えることを考えた」
これらはすべて止め写しの応用です。映画が誕生して間もない時期に、遠く離れたアメリカ、フランス、そして日本で同じようなことが考えられていたことからみても、人の考えることはみな同じ、映画言語は世界共通、の感があるのです。
つづく
★次回もジョルジュ・メリエスの話を続けます。
040 メリエスのハンドメードのカラー映画 [草創期の映画]
040 ハンドメードのカラー映画
ノンフィクションとフィクション-3
ジョルジュ・メリエス
●ハンドペインティングによる色彩映画「さなぎと黄金の蝶」1900
前回に続いて、ジョルジュ・メリエスのお話です。
●クリエイティブは、まず真似ることから。
1896(M29)年後半に作られた50フィート(17m)1分弱の短編映画(当時はシネマと言う言葉が無く、フォト・アニメと呼ばれた)「ロベール・ウーダン劇場における婦人の雲隠れ」(前回に記事)。この作品はジョルジュ・メリエスの名をいっぺんに高めるほどの話題を呼びました。その陰にはマジシャンとしての自負がありました。彼はシャルル・パテに、「あなたの撮影機を買いたいのですが、フィルムが高すぎませんか。こう言っちゃ何ですが、いつも広場の情景や兵隊の行進だけじゃ飽きられてしまいますよ」と言われたことが気になっていたのでした。
●左/シャルル・パテ 後に映画会社「パテ・フレール」を興す
右/ロンドンの映画事業主 ロバート・ポール
シャルル・パテはすでに述べたように、1877年(M10)以降、エジソンが発明した蝋管蓄音機の亜流を安売りして地盤を築いた事業家です。次にエディスンが「キネトスコープ」 を発表すると、ロンドンのロバート・ポールに接触して亜流の「キネトスコープ」を作らせ、販売していました。また、リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」初公開にも参加し、メリエス同様「シネマトグラフ」を譲って欲しいとリュミエール兄弟に申し出て断られた一人でもありました。
その直後にメリエスが開発した優れもの映写機「キネトグラフ」にも関心を示し、そのフィルムとともに何とか自分の事業に加えたかったようなのですが、その話はしばらくそのままになっていました。
1896年にパテ・フレール社を興したばかりのパテは、まだ自身でフィルムの作り方が分からず、リュミエール社が作るフィルムをそのまま真似て作り始めていました。いわば剽窃ですが、何ごとも初めは真似ることから。
それはゴーモン社もメリエスも同じこと。リュミエール兄弟の「○○駅への列車の到着」や「○○の出口」といったフィルムが、所を変えてたくさん作り出されました。エディスン社すらこのあとメリエスのフィルムをそっくり真似て、アメリカで販売したりすることになるのです。当時はまだ著作権という考え方はなく、この時代のこの業界は "やった者勝ち" という様相だったのです。
●メリエスの最初の長編映画は、色彩映画だった
メリエス自身、パテに言われるまでもなく、オリジナリティのあるもっと長い作品に挑戦しようと考えていました。それも白黒ではなく、色彩映画でした。動かない写真がスクリーンの上で動いたとたんに、人は現実の情景と同じ色彩を映画に求めたからです。
当時はまだカラーフィルムが科学的に完成していませんから、人工着色です。着色映画は、すでにエディスン社の「アナベルのダンス」がありました(制作者はチャールズ・ジェンキンス)が、それは文字通りアナベルというダンサーが踊っているだけのフィルムでした。メリエスはその3倍以上の200フィート(60m)、約3分におよぶ物語映画を作ることにしたのです。映画で物語を見せるという初めての試みに、ジョルジュ・メリエスは挑戦したのです。
タイトルは「悪魔の館」。メリエスがステージでも演じていたお得意の悪魔の扮装から思いついたトリック映画です。王女のところに悪魔が現れるが、何とか退散させると次に現れたのはイケメン男。王女は安心して手を差し伸べると、男は悪魔の本性を現して王女をさらっていく、というような物語です。
この映画は、もちろん止め写しと置き換えのトリックがふんだんに使われましたし、新たに溶暗・溶明(フェード)、およびそれを重ねたオーバーラップ(二重露光)のテクニックが用いられました。これらはすべて撮影の段階で行う必要があるため、とても微妙なテクニックを要します。またトリックは現像上も細かい調整が必要であり、これはフィルム現像も自社で行っていたからこそできたハイテクニックでした。
●映画撮影スタジオとしては世界初
トリック撮影に欠かせないのは光量です。メリエスは「悪魔の館」を撮りながら、明暗を自在に調整できる撮影環境の必要性を感じました。エディスン社の「ブラック・マリア」のようなものではなく、もっと本格的な撮影スタジオです。メリエスはモントルイユにある別荘の庭にそれを建てることにしました。
●世界初、メリエスの映画撮影スタジオ 最初の光源は自然光 1897
世の中に無いものを作るのですから、設計から設備から何から何までをメリエスが考え、早速実行に移しました。 奥行き17メートル、幅7メートル。屋根と周囲には摺りガラスを張り、天井に張ったキャンバスは滑車を使った操作で開閉し、採光を調整できるようになっていました。人工照明の必要性も感じられて、アーク灯と水銀灯がそれぞれ15本ずつ設置されました。一方には板張りのステージ。バックヤードには楽屋や衣裳部屋も設けられました。
●メリエスの映画撮影スタジオ 外観 1897
こうして1897(M30)年3月、世界初と呼べる本格的撮影スタジオ(当時はスタジオと言う言葉はなく、アトリエまたはグラス・ステージと呼ばれた)は発足しました。照明はあっても太陽光にはかなわず、朝11時から午後3時までが撮影時間でした。ステージの上下にはその後トリック撮影を行うための吊り具や何層もの書割、上下のせりなど、演劇の舞台設備同様の装置が施されることになります。
●色彩映画のための大規模彩色スタジオ
メリエスは撮影スタジオ作りの一方で、もう一つの工場作りも進めていました。それは彩色アトリエです。女工さんを集め、養成しながら、出来上がったポジフィルムに1コマずつアニリン染料で色を塗っていくのです。一人が1色を担当し、多い時には20色以上使うこともあったそうです。写真を見るとそのスケールに圧倒されてしまいますね。
●さながらアニメスタジオのような、メリエスの「彩色アトリエ」1897
無声映画は1秒16コマ。3分では2,780コマ。色ごとに班が組まれて、自分の担当する色の部分だけを全コマ塗り終えたら、次の色の担当に渡すという作業が、拡大鏡を覗きながら行われていた訳です。
それをプリントの本数だけ塗る訳ですから、気の遠くなるような作業です。ただ、これは当時としては初めて生まれた最先端の仕事です。家内制手工業に慣れたその頃の女工さんにとっては、苦痛どころかむしろ目新しく、誇らしい仕事ではなかったでしょうか。ジョルジュ・メリエス初の色彩映画「悪魔の館」はこうして生まれたのでした。
(この流れ作業とも呼べる生産方式は、1908年、ヘンリー・フォードがT型フォードの生産で考え出したベルトコンベアシステムよりも早かったと見ることができると思います)
●映画で広がったメリエスの魔法の領域
メリエスが映画を撮り始めたのは1896(M29)年の春から。その1年間で彼が制作したフィルムは80本にも及びます。1本50フィートのフィルムで上映時間はほぼ1分という作品がほとんどで、内容は実写が多かったのですが、後半では歴史再現やトリックが増え、メリエスの特質がはっきりしてきます。この製作本数は、彼がいかに精力的に映画づくりに取り組んだかを物語っています。
そして重要なことは、監督や大道具小道具、衣装、照明・・・というように、必要に応じて自然発生的に進んだ役割分担が「分業」を形成してきたこと。それはこれまで、エディスンにもリュミエール兄弟にとっても、海のものとも山のものとも分からなかった映画が、産業の様相を見せ始めたということなのです。
●メリエス映画の真骨頂、マジック・ファンタジー
それではこの辺で、私の大好きなジョルジュ・メリエスの作品を3本ご覧いただきましょう。
製作年度は1900年から1909年に亘りますが、2本は彩色映画です。1本ずつその手法を解説していたらプログ1本分になってしまいそうなほど、メリエスの才覚とトリックの妙味がたっぷりと味わえる作品です。それぞれどのようなトリックが使われ、どのように撮影されたかを推測しなからご覧いただくと、興味も倍増するのではないでしょうか。
■「一人オーケストラ」1900
メリエス自身の一人七役。七重露光というとんでもない多重露光作品。1本のフィルムに7回撮影を繰り返したものですが、7人の演技のタイミングがこれほどぴったり合っているのは、まさに神業。どのようにして合わせたのでしょうね。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
■「さなぎと黄金の蝶」1900
メリエスとジュアンヌによるエキゾチックファンタジー。さなぎをチョウに変えた魔法使いが、奥方の怒りに触れてさなぎに変えられてしまう。お得意の止め写しと差し替えがふんだんに生かされたコメディです。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
■「悪魔の下宿人」1909
映画という魔法を手に入れたメリエス扮する悪魔の魔術師にとっては、部屋にあるものを片っ端から消滅させてしまうことなど朝飯前。それにしてもこのアイディアの豊かさには敬服。まずは驚嘆すべき連続トリックの妙味をご堪能ください。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
注/3本とも実際よりも短い長さであることをご了承ください。
次回もジョルジュ・メリエスの作品でお楽しみいただきます。
041 世界初。女流映画監督登場。 [草創期の映画]
世紀末、混迷の映画世界-1
「ゴーモン社」「パテ・フレール社」「スター・フィルム社」
●時代背景/19世紀末 パリ、シャトレ広場
20世紀まであと5年という1895年12月28日に誕生した映画(フォト・アニメ)は、わずか1~2年のうちに、リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」 とそれに続くトーマス・エディスンの「ヴァイタスコープ」を中心に(中心にと言うのは、亜流も出回ったから)、あっという間に世界中に広がりました。映画は誰もまだ体験したことの無かった驚きを伴って19世紀末を彩りました。それはまた、映画がたどるべき道を模索する混迷と葛藤の始まりでもありました。
今回はパリを中心に、2,000年に至るまでの関係者の動向を追ってみることにしましょう。
●フランスでは、リュミエール兄弟、メリエス、パテ、ゴーモン
「シネマトグラフ」と「ヴァイタスコープ」の登場は、直ちに世界中で映画市場と言う全く新しいマーケットを急速に形成しつつありました。1896年。フランスではリュミエール社をトップに、2番手にトリック映画という独自の展開を編み出したジョルジュ・メリエスが付き、3番手はシャルルとエミールのパテ・フレール(パテ兄弟)社。レオン・ゴーモンのゴーモン社は少し遅れて映画製作を開始しました。遅れた理由は新しい撮影機を開発していたためで、そのカメラは「クロノ・ゴーモン」という名で1897年春に誕生します。
●アリス・ギイ ●レオン・ゴーモン
そのカメラを回してゴーモン社で初めて映画を撮影したのは、秘書のアリス・ギイでした。ゴーモンが会社の近くを借りて用意させたガラス屋根つきのにわか仕立てのスタジオで、絵描きが背景を書き、衣装は彼女自身が買い集め、出演者は彼女の友だちでした。出来上がったフィルムはさながら学芸会のようでしたが、こうしてゴーモン社の第一作は完成しました。
アリス・ギイは間もなくゴーモン社の映画製作責任者(プロデューサー)に就任。自ら脚本を書き、演出に当たるようになります。彼女が本当に手腕を発揮するようになるのは20世紀に入ってからですが、彼女は名実ともにゴーモン社の基盤を築いた一人でした。彼女の活躍もあって、ゴーモン社は1898年にロンドンに支社を設置するまでに成長します。
このように映画は、映画製作と機材の製造販売の2本立て事業に本腰を入れるデペロパーのような役割を担った人たちの手で世界の隅から隅まで広がって行ったのですが、その市場を先導していたリュミエール社は、地元フランスはもちろんのこと、1896年にはすでにニューヨークにも支社を開設していました。
●もうすっかりおなじみのリュミエール兄弟。
●チャリティ・バザールの大惨事とメリエスの健闘。
ところが1897年の5月。大変な事件が発生しました。シャンゼリゼ大通りの近くに開設される恒例の「チャリティ・バザール」での出来事です。この慈善イベントは、「パリの名士年鑑に載っている人たちに会えたかったらそこに行け」、と言われるほど、パリでもっとも優雅なイベントとして知られていました。貴族や名士の娘など上流階級の着飾った貴婦人たちが自分たちの古着を売り、その売上金を施設に寄付するのです。会場には簡素なつくりの売店、屋台、レストランといっしょに、一番の目玉として人寄せの映画館が作られていました。
●当時の光学的な見世物小屋(この事件とは関係ありません)
短期の催しですから、映画館といっても外光を遮られる程度の板張りの粗雑な小屋造りです。映画の上映には簡便な光源としてエーテルランプを使っていたのですが、映写技師が操作を誤ったためにフィルムに引火。当時のフィルムはニトロセルロースですから、爆発的に燃え上がったフィルムから火災が発生し、わずか2~3分で映画館全体が火の海になってしまったのです。
出口は一方しかなく、逃げ惑う人たちは次々と煙に巻かれました。火災は瞬く間にバザール会場全体に広がり、あれよあれよという間に死者117人という大惨事になってしまいました。
翌日の「プチ・ジュルナル」紙は、この事件をトップの全頁を使ってセンセーショナルに報道。公爵夫人はじめ貴族階級の婦人たちまでもその犠牲となったということで、人々は恐怖におびえ、映画は危険なものというイメージがあっという間にフランス中に広まってしまいました。
●バザールの大惨事を伝える「プチ・ジュルナル」紙。
この事件は、どこを覗いても同じようなフィルムしかやっていない映画に対する人々の飽き飽きムードを加速させることになりました。「シネマトグラフ」誕生から1年半ほどで、本場のフランスでは早くも〈フォト・アニメ〉と呼ぶ映画に危機感が漂い始めたのです。
その遠のき始めた足取りを止め、人々を呼び戻したもの。それが次から次へと発表されるメリエスの奇想天外な作品群でした。メリエスのフィルムに対する人々の熱狂は特別でした。
●ジョルジュ・メリエス ●ジュアンヌ・ダルシー
こうした期待と声援を背景に、1897年7月、メリエスはスター・フィルム社を設立しました。この年だけで製作された作品数は、短いとはいえ80本近くにもおよびました。
この時点で代表的な作品は「呪われた宿」「催眠術師」「悪魔の魔術」「いくつもの頭を持つ男」「分身の魔術」など、お得意の幻想的な作品が多いのですが、いずれも1巻約1分という作品です。ただ、作品の評価は長さや製作本数ではありません。それだけのアイディアが考えられたというところが他社の追随を許さないところだと思います。
●資金をめぐる皮肉な巡り合わせ。
さて、バザールでの惨事が一段落した頃、メリエスの元にルイ・グリヴォラスと名乗る一人の紳士が訪れました。彼は機械工場を経営している資産家で、奇術アカデミー会員でもありました。以前からメリエスの映画を見て感動し、資金提供を申し出たのです。ところがタイミングが悪かった。メリエスは、その直前に似たような話を持ち込まれて詐欺に遭い、2万5千フランを失ったばかりだったのです。
メリエスはすべて自分の力でこれまでやってきたのに、人の力を当てにして失敗したことをとても後悔していました。そこでグリヴォラスの話は無かったものと考え、彼の申し出を丁重に断りました。
●ルイ・グリヴォラス ●シャルル・パテ
グリヴォラスは「それは残念なことですね」と仕方なく引き下がりましたが、次に有望と感じていたシャルル・パテにその話を持ち込みました。
グリヴォラスは電気工学の技術者でした。1875年に興した会社が時代の花形である電気器具の製造・販売で成功し、銀行、財団の支援を受け、資本金100万フランで経営していました。彼自身マジックを趣味とし、メリエスに傾倒していたのですが、断られたため、次に事業として映画を展開しそうなパテ兄弟に図ってみたのでしょう。
シャルルとエミールのパテ兄弟は、前年に兄弟たち身内の出資でパテ・フレール社を興したばかりでした。ところがここに10万フランというグリヴォラスの資金援助の話が転がり込んできたのです。パテ兄弟にとっては渡りに船。そこで兄弟は映画事業に本腰を入れる決心が整いました。1897年12月のことです。
パテ兄弟の目には事業としての映画の将来性がうっすらと見えてきていました。それに対してメリエスはあくまでも芸術家でした。会社を大きくする事業よりも、映画づくりそのものに打ち込んだのです。そこがある意味で人生の分かれ目のようなところがあるのですが、メリエスにとっては例えその結果がシャルル・パテと対照的になろうとも、彼の人生に悔いは無かったのではないでしょうか。
ですが、それはまだ20年以上も先の話。メリエスのスター・フィルム社は1900年までの5年間、作品数でパテ社の2倍ものフィルムを作り出すほどの活況を呈し、20世紀を迎えてからのメリエスは、(マジックを使わずに)もっともっと大きな花を咲かせて見せるのです。
つづく
●今回も大好きなジョルジュ・メリエスの2作品をどうぞ。
■「現代の魔術師」1898 40秒
現代の…とは、あくまでも映画によるトリックを手にした1898年の…という意味。メリエス自身と看板女優ジュアンヌのデュエットで演じられていますが、その呼吸は、さすが恋人同士ならではですね。止め写し&差し替えの最高傑作!
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
■「ゴム頭の男」1902 80秒
メリエス短編の傑作中の傑作。こうした発想が浮かぶのは、ゴムのように柔軟な頭を持つメリエスならでは、ですね。その仕掛けを下に示します。
二重撮影による一人二役と、遠近法を利用したトリックです。
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
042 元祖「シンデレラ」実写版。 [草創期の映画]
042「シンデレラ」実写版元祖はジョルジュ・メリエス。
19世紀末、混迷の映画世界-2
リュミエール社の転換とメリエスの進展
●ジョルジュ・メリエスの「シンデレラ」1899
中央は「12時までよ」と指差す妖精 右がシンデレラ
前回からの続きです。
●リュミエール社とAMCの追い上げで窮まったエディスン社
リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」は、1896(M29)年早々から始められた「シネマトグラフ世界紀行取材班」ともいうべき技術者の海外派遣が大きなPR効果をもたらし、その名は機材、フィルムともにたちまち世界に広がりました。リュミエール社は本国フランスはもちろん、この年の春にはニューヨーク、ブロードウェイにアメリカ支社を開設すると、全土の主要都市に事業の手を広げ、翌1897(M30)年には支社を拡張しなければならないほどの勢いがありました。●リュミエール兄弟
再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら
●登場したばかりの自動車のパレードを撮影したリュミエール社のフィルム2種 1896(M29)
自動車は馬の代わりにエンジンが搭載されただけ。スピードも自転車並みということが分かる。
最初のフィルムで゛は、画面中央に手回しで撮影しているカメラマンの姿も写っている。
トーマス・エディスンが1896(M29)年4月にようやく市場に送り出した「ヴァイタスコープ」 は、リュミエール兄弟に遅れることわずか4ヶ月でしたが、すでに市場は先発の「シネマトグラフ」に抑えられていました。「ヴァイタスコープ」はデビュー当時はエジソンの名前によってそこそこ売れたものの、あとがまったく振るいませんでした。
●トーマス・エディスン ●元エディスン社社員、現AMC所属
ウィリアム・ディクスン
その上エディスン社は、ウィリアム・ディクスンが転籍した「アメリカン・ミュートスコープ・カンパニー(AMC)」からも、「ミュート・スコープ」と新鋭の映写機「バイオグラフ」によって、「キネトスコープ」の事業を断念せざるを得ないところまで追い上げられていました。
この時点でエディスンン社は、「キネトスコープ」の役割は終わったと考え、専属代理店だったラフ&ギャモン商会をお役御免として切り捨てました。エディスン社が次の上映式「ヴァイタスコープ」を手にするお膳立てをしてくれた会社です。エディスン個人はその功績を考え、ラフ&ギャモン商会との決別を苦悩したことでしょう。ところがそういうシビアな処断は、大抵営業部長のウィリアム・ギルモアかお抱えの法律家フランク・ダイヤーによってなされるのでした。ところがここにまた、エディスンに救いの神が現れます。
●ディクスンの退社後、
エジソン社に営業部長として君臨するウィリアム・ギルモア
●エディスン社がトーマス・アーマットに改造させた「上映式ヴァイタスコープ」
●リュミエール社、アメリカから撤退
1897(M30)年3月。「アメリカはアメリカ人の手で」と自国の産業保護政策をアピールしていた共和党のウィリアム・マッキンリーが大統領に選ばれたのです。これは明らかにアメリカの競争相手をターゲットにした排他政策で、「遡及効果を持つ保護主義」によって外国製品には過去に遡って高い関税が課せられることになりました。
当時はアメリカも家内工業から資本主義への転換期で、事業家は市場の独占を目指しました。が、その前に外国企業を締め出す必要がありました。フランスのリュミエール社はその矢面に立たされることになったのです。
リュミエール兄弟は初めから、「シネマトグラフ」にはエディスンの(実はウィリアム・ディクスンの)考案によるフィルム仕様(幅やパーフォレーション)を前提にしていることを否定していませんでしたが、案の定、エディスン社はリュミエール社に対して特許侵害の訴訟を起こしました。また、税関からは「遡及」による不法輸入罪をでっち上げられる始末。アメリカ支社の支配人はたまらず、7月末、ハドソン河から汽船でフランスへ逃亡を図るという事件にまで発展しました。
●リュミエール兄弟の最初の「シネマトグラフ」
その年の末、リュミエール兄弟は不本意ながらアメリカから撤退することにしました。こうしてリュミエール社のアメリカでの活動は1年半ほど、ニューヨークではわずか4ヶ月ほどの短期間で幕を下ろすことになったのでした。リュミエール兄弟はそれまで展開していた「シネマトグラフ」技術者の海外派遣も止めざるを得なくなりました。こうして一時は世界産業にまで発展したリュミエール社でしたが、いちばん反応の良かったアメリカから追い払われてしまったのでした。
1898(M31)年9月、リュミエール社は、それまで誰にも売らなかった方針を曲げて、「シネマトグラフ」の販売を決意しました。けれどもその頃には、前年に誕生したレオン・ゴーモンの映写機「クロノ・ゴーモン」の方が優れた機能を備えていました。映画制作は続けられましたが、年間400本だったレベルが50本程度にまで縮小されました。ただし、それまでに作られた1,000本にもおよぶリュミエール社の映画は、依然として世界中で高い人気を維持していたことは言うまでもありません。
●新機軸に向けて動き出したリュミエール兄弟
リュミエール兄弟は元々技術者でしたから、作品を作るよりも映写機や写真機の製造と写真技術に専念することに方向転換しました。この時代の映画は見世物でしたから、もっぱらヴォードヴィルやバーレスク、ミュージックホールなどの幕間に上映されていたのですが、リュミエール兄弟はそれまでに得た手ごたえから、映写機器や上映設備を考える中から映画専門の環境づくりに考えが及び、これは20世紀に入って世界で初めての「映画館」の誕生につながっていきます。
また一方では、1900年に控えた世紀のビッグイベント「パリ万国博覧会」に向けて、映画の新たな可能性をアピールするため、大スクリーンでの上映や立体映画の開発に力を入れていくことになります。
●19世紀末には映画館は存在せず、通常はヴォードヴィル劇場のようなところで上映されていた。
●メリエス、長編作に新境地
リュミエール兄弟が実写の特性をそのまま生かした記録やニュース性のあるものを制作していたのに対して、ジョルジュ・メリエスは自分が行ってきたマジックを映画のトリックという方法に置き換えながら、最初から物語性のある映画を作ってきました。
数々の短編で腕を磨いたメリエスが、スター・フィルム社として(当時としては)本格的な長編に臨んだのが、1899(M32)年の「ドレフュス事件」と「シンデレラ」でした。いわば「シンデレラ」実写版の元祖ともいうべき作品です。
●もうおなじみの ジョルジュ・メリエス
ドレフュス事件は、なんとその前年に起こった現実の出来事です。軍の情報をドイツに売り渡したスパイの疑いで裁かれたフランス陸軍のアルフレッド・ドレフュス大尉が国家反逆罪に問われ、南米ギアナ(ガイアナ)の悪魔島に流刑されますが、弟の懸命の努力で無罪の証拠が挙げられ、クレマンソーやゾラの支持もあって軍の上層部にまで捜査が及んだ結果、陰謀であったことが判明して無罪となった、という事件です。
●「ドレフュス事件」1899 11分
メリエスの「ドレフュス事件」は、それをあたかも実写記録のように見せた再現劇として構成されました。注目すべきは20メートルのフィルム12本を使い、11の場面で構成したことです。
例によって1巻のフィルムを撮影機を据え置いたまま回し切る撮影技法は変わらず、1シーンごとにそのつど完結しますが、今日のように連続した1本の映画として上映すると11分ほどかかる11シーンのドラマがここに現れたということです。有名な事件ですから、観客は場面を見ただけでそのなり行きは分かっています。この映画が本物のようなリアルさで大評判を呼んだことは想像に固くありません。
このように、現実の事件をドラマチックに再構成してみせる手法は、のちにセミ・ドキュメンタリーと呼ばれるようになります。
なお、ドレフュス事件が解決しないうちに、当時の大統領が暗殺されるという事件が発生します。軍を守るために裁判のやり直しを断固として拒否したことが原因だとされていますが、メリエスはその大統領の葬儀を撮影しています。この実写記録は今でいうニュース映画のさきがけともいうべきものでしょう。
●ドレフュス事件 1899 イリュストラシオン誌の写真 (メリエスの映画ではありません)
●史上初のシンデレラ映画、ジョルジュ・メリエス監督「シンデレラ」1899
全20シーンの第6シーン
このあと、結婚式、婚礼の行列、花嫁花婿のバレエなど、盛りだくさんです。
116年前の人たちが観た 元祖・実写版「シンデレラ」。
どうぞお楽しみください。
●「シンデレラ」1899 5分50秒
「シンデレラ」でメリエスは、「ドレフュス事件」の成功を更に発展させました。長さは「ドレフュス事件」の約半分。120メートルですが、メリエスは主な興行主へはカラーで配給することを考えていました。それは他社の追随を許さない彩色アトリエを擁するスター・フィルム社ならではの企画でした。
原作に忠実にと描かれた絵コンテは20ものシーンになりました。登場するキャラクターはなんと35人。文字通り絢爛豪華なコスチュームプレイです。主要な役者はシャトレ劇場やフォーリー・ベルジェールからスカウト。シンデレラに魔法をかける妖精役はモンマルトルのキャバレーの踊り子でした。
妖精の魔法によって、ネズミが御者に、カボチャが馬車に変わるところなど、まさにメリエスのために書かれたような物語。例によって止め写し、ディゾルヴ(多重露出)をふんだんに使ったトリッキーなアクションが、彼のロベール・ウーダン劇場に押しかけた観客を沸かせました。そしてその反響はフランスに留まらず、イギリスにまで及びました。
これらの大作映画になると登場人物の衣装を制作することも大仕事です。モントルイユの撮影所に隣接するコスチュームアトリエでは、10数人もの女工が、メリエス夫人の指示の元で衣装作りに励んでいました。
●スター・フィルム社のコスチューム・アトリエ
長編映画が成功するとメリエスは、従来の1巻20メートル(手回しで約1分)というフィルムの制約を破り、20世紀に入ると次第に100メートル以上の作品に主力を注ぐようになります。ようやく、1作1シーン1分、というチョー短編映画の時代が終わりを告げたのでした。
つづく
★次回は、エディスン社と、同社と決別したウィリアム・ディクスン所属の「AMC」の抗争を中心に…
※フィルムの長さの表記で、メートルとフィートが混在していますが、参考資料を重んじ、換算せずにそのまま記述することにしています。それは当時、フィルムの長さはオーダーメードで作られることもあり、フィートとメートルの両方で作られた可能性があると思われるからです。
※なお、撮影には生フィルムを使うため、フィルムの最初と最後は感光することを前提に(リーダーと言いますが)長めに作られているはずです。けれども、表記の20mは実質的な長さと考えております。
★「ドレフュス事件」「シンデレラ」はYOUtube kaliyamashitaさんの動画を使わせていただきました。
043 それはエディスン社の勝手でしょ。 [草創期の映画]
043 エディスン社の専横、始まる。
19世紀末、混迷の映画世界-3
●時代背景 19世紀末・ニューヨーク
前回からの続きです。
世界企業に成長したフランスのリュミエール社。それが、米国マッキンリー大統領による保護政策でアメリカからの撤退を余儀なくされました。目の上のたんこぶが取り除かれたエディスン社は、国内に台頭したライバル、アメリカン・ミュートスコープ社(AMC)との抗争に本腰を入れる状況が整いました。
●エディスン社とAMCとの関係について
両者の関係については前に書きましたが、簡単におさらいしておきましょう。
1895年10月、トーマス・エディスンと決別してエディスン社を退社したウィリアム・ディクスンが製作部長として迎えられたAMCでは、ディクスンがエディスンの特許に触れないように考えた同じ覗き見式の「ミュートスコープ」を市場に投入して、エディスン系「キネトスコープパーラー」に追い打ちをかけました。
機械の外観もスマートで、画面が大きく鮮明映像が楽しめるAMCの「ミュートスコープ」は、たちまちエディスン社の息のかかった「キネトスコープパーラー」の市場を席巻するほどの勢いを見せました。
●左、中/エディスン社系「キネトスコープパーラー」と「キネトスコープ」
右、AMCの「ミュートスコープ」
同時にAMCは「バイオスコープ」と呼ぶ撮影機と「バイオグラフ」と呼ぶ映写機を開発して、上映方式の先手を取りました。
エディスン社は覗き見式の「キネトスコープパーラー」が成り立たなくなったところに、タイミング良く、トーマス・アーマットが上映式「ファンタスコープ」をエジソン社直系の代理店「ラフ&ギャモン商会」に持ち込んだので、エディスン社では得たりとばかりに翌1896年4月、アーマットに改造させた「ヴァイタスコープ」を急きょ発表して、ようやく映写機開発競争に追いつくことができました。
そこに1897年末、リュミエール社の「シネマトグラフ」がアメリカから放逐されるという追い風が吹き、エディスン社も活気を取り戻しましたが、その前にはAMCが立ちはだかっている、というところまでです。

●トーマス・アーマットと彼の「ファンタスコープ」
●アーマットがエディスン社で「ファンタスコープ」を改造して完成させた「ヴァイタスコープ」●リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」
●AMCでディクスンは、製作現場で大活躍
ところで、1896年の大統領選挙運動で活躍したのがAMCでした。AMCは大統領候補ウィリアム・マッキンリーの執務風景を撮影したフィルムの最後に、はためくアメリカ国旗をモンタージュした宣伝映画を制作しています。これは世界初の選挙PR映画といえるでしょう。
マッキンリーが大統領になると、AMCはその弟を顧問に迎え、政界とのパイプを強固にしました。●AMC製作部長のウィリアム・ディクスン
一方、ライバルのリュミエール社がアメリカから撤退する以前から、ディクスンはAMCの監督として、改造を加えた「バイオスコープ」で自社作品を撮り始めました。さし当たってはマッキンリー大統領の国内歴訪の旅に随行した記録映画でしたが、1899年秋には南アフリカに赴き、ボーア戦争(南アフリカとイギリスの戦争)の戦場で望遠レンズを利用したパノラマ撮影も行っています。当時の大方の映画開発者の例にもれず、元は技術者でありながら監督もこなすセンスの持ち主だったようです。
このようにAMCはもっぱら真実の記録を目指していましたが、エディスン社は対照的に娯楽作品を目指していました。
●エディスン社「ブラックダイアモンド・エクスプレス」1897
●エディスン社のはかりごと
エディスン社としては、映画の開発でフランスのリュミエール社に立ち遅れたとはいえ、アメリカでは先発です。何が何でも後発のAMCにその座を譲るわけには行きません。映写機で後れをとったAMCを引き離すには、戦略しかありません。エディスン社にはそういう時のために、営業部長ウィリアム・ギルモアと法律家フランク・ダイヤーを筆頭とするやり手の顧問弁護士たちが抱えられているのです。 ●エディスン社営業部長、ウィリアム・ギルモア
●エディスン社営業部長、ウィリアム・ギルモア
彼らがAMCの独走を指をくわえて見ているはずはありません。こういう場合を考えて手は打ってあったのです。それは、6年も前に申請してボツになってしまった撮影機の特許の申請内容に、AMCの「バイオスコープ」に対抗できる機構になるように修正項目を追加して、別の特許として申請しておいたのでした。6年も前のことを知る特許の審査員は少ないでしょう。これはそこを読んだエディスン社が仕掛けた起死回生策ともいうべき巧妙なトリックでした。
●急を告げるAMCとエディスン社の抗争
それは1897年3月に始まりました。特許庁は抵触審査を行うことを宣言しました。同じような特許が出願された場合、どちらに優先権があるかを審査するものです。
最初はAMCに有利に展開しました。写真を動かしそれを上映する技術はすでに何人もの発明家が不満足ながらも実現している上、発明が2年以上経っても行使されない場合は無効であることを理由に、特許庁はエディスン社の主張を取り下げました。
AMCは、それでエディスン社の特許申請は無効、と胸をなで下ろしたのですが、その考えは甘かった。その程度で引く位なら最初から仕掛けてはいないエディスン側でした。
不利と分かるとエディスン社は、特許局長に直談判を行いました。その動きを察知したAMCは、エディスン社が申請した特許を保留にするように特許局長に申し入れました。このあたりが私立探偵社の出番です。双方の間に激しいスパイ合戦が繰り広げられたことは想像に固くありません。
その結果、エディスン社の法律顧問フランク・ダイヤーがどのように話を進めたものか、AMCの申し入れは却下されてしまったのです。 ●トーマス・エディスン
●トーマス・エディスン
こうして1901年7月、「映画撮影機の発明者はトーマス・エディスンである」、ということが認められました(「映画」の発明ではなく「撮影機」の発明が認められたのですが、一般に映画の発明はエディスンと言われるゆえんです)。これでトーマス・エティスンは、映画という新しいジャンルにおいても「発明王エディスン」の誇り高き名を天下に認めさせることができるようになった訳です。エディスン社はそれを錦の御旗として(古い!)、早速、特許の権利の行使に入りました。
エディスン社は、当時、雨後の竹の子のように登場し始めた小規模な興行会社や機材販売会社に対して、撮影機の製造とフィルムのコピーを禁止するとともに、興行の場合は入場料に対する一定の歩合を収めるように通告しました。
その結果、翌年春までだけでも、亜流の撮影機を作って販売していた7社ほどがまず告訴されました。それをきっかけにこの件に関する訴訟は20世紀に入ってからも続けられていきます。
これは一見、特許権を持つ者として当然の権利行使に見えますが、その裏には、将来性が見えてきた映画という新しい産業を押さえるのは今、というエディスン社の強い意志が露骨に見え隠れしていることに関係者は気づいていました。エディスン、この年50歳。
●エドウィン・S・ポーター、エディスン社に入社。
エディスン社がこのような係争をはじめていた1897年(1899、1900の説もあり)、一人の若者がエディスン社を訪ねてきました。彼は「エドウィン・スタントン・ポーター、ペンシルベニア生まれの27歳です」と名乗りました。アメリカ海軍で電気技師として勤務したのち除隊。セールスマンをやっていたのですが、新しい映画の仕事に興味を持ったということでした。
当時は映画の作り方を教えてくれる先輩がいるわけではありません。当初は単に情景を撮ったり、ニュースのようなフィルムを撮影するカメラ助手から始まりました。
ポーターの興味は、本来動かない写真がなぜ動くのかという点でした。彼は撮影された35ミリフィルムを透かして見ました。同じような写真が連続しているだけです。ヴァイタスコープ(エディスン社の映写機)に掛けて、ハンドルを回してみました。すると見事に動きが生まれます。早く回したり、遅く回したり、逆に回したり、いろいろ試してみるのはごく自然な成り行きでした。
こうした作業や思考を重ねる中から、彼は後に述べることになる映画史に残る作品を生み出すことになります。その作品とは「アメリカ消防夫の生活」と「大列車強盗」の2作ですが、このブログではまだまだ先のお話です。
●「大列車強盗」エドウィン・ポーター 1903 この件については まだ先になります。
●AMC、バイオグラフ社に社名変更
ところで、AMCとエディスン社の関係は振り出しに戻り、ついに裁判に持ち込まれました。
エディスン社の論理は巧妙でした。裁判にはトーマス・エディスンも召還されました。AMCはそこで最後の切り札を出しました。エディスンが発明したという「ヴァイタスコープ」の母体は、トーマス・アーマットが考案したものではないかと迫ったのです。
エディスン社との係争の途中、1899年にAMCは、ディクスンが開発に参画した「バイオグラフ」の名を冠して「アメリカン・ミュートスコープ&バイオグラフ社」(以後、バイオグラフ社と表記)となりましたが、こうしてエディスン社を揺さぶっておいて、バイオグラフ社は、お互いの利益にならない敵対関係を収めようと、調停に持ち込みました。
銀行と投資家をバックにもつ同社は、この年の末に50万ドルでエディスン社の〈動く写真〉に関する権利をすべて買い取ることを申し出ました。エディスン社も理解を示し、ようやく和解が成立したかに見えました。
ところが、1900年末にバイオグラフ社が最初の30万ドルを支払う段階になって、皮肉なことに突如として経済危機が襲い、銀行が破産してしまったのです。そしてまた話はご破算となり、結局、1901年7月にエディスン社が裁判に勝利しました。バイオグラフ社は1897年に遡って賠償金を支払わなければならないことになったのでした。
このような経過を経て、欧米における映画事業は次第にエディスン社の思惑通り、その腕に抱え込まれていきます。エディスン社の専横ともいえるこの施策は、20世紀に入ると、映画の振興に比例するように更に拡大していきます。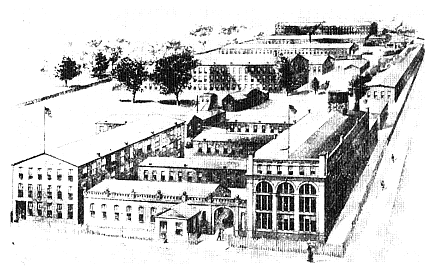
●ニューヨーク郊外ウェスト・オレンジのエジソン研究所 1900
●ヴァイタグラフ社の登場
ところで1898年3月に、アメリカにまた一つ、新しい映画会社が誕生しました。
ジェームズ・スチュアート・ブラックトンとアルバート・スミスは、エディスンの初期の映写式「キネトスコープ」を購入しましたが、市場に出回っているフィルムよりも自分たちの方がもっと面白いフィルムを作れると考え、その映写機を撮影機に改良して「ヴァイタグラフ」と名づけました。
その後、同じくエディスン社の「ヴァイタスコープ」の営業権をもつ巡回興行師ウィリアム・ロック(ポップ・ロック)と出会い、楽しい映画を作ることで考えが一致。1898年の夏、「屋上の夜盗」という映画を撮りました。泥棒と警官による単純な追いつ追われつのドタバタ喜劇なのですが、滑稽なギャグが人気を呼んだことに自信を得た3人は、共同でヴァイタグラフ社を興します。
この会社はやがてスチュアート・ブラックトンによるアニメーションをはじめ、初期のアメリカ映画を代表する作品を生み出していくことになります。
アメリカにおいては、エディスン社、バイオグラフ社、ヴァイタグラフ社。フランスにおいては、リュミエール社、メリエスのスター・フィルム社、パテ社、ゴーモン社……
ここに、映画創生期における欧米の代表的な映画会社が揃いました。とはいえ、技術的には相変わらずモノクロ、サイレント。そして駆動は手回しの時代です。
つづく
◆20世紀の段階に入る前に、この辺りで日本の動向に触れておきたいと思います。
次回と次々回は「日本映画事始め」を予定しております。


















